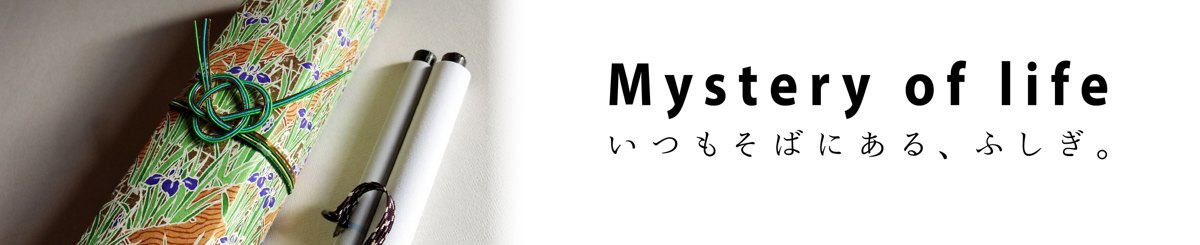【説明】
インドの神で、仏教に取り入れられ台所の神とされた。大国主命の別の姿ともされる。
ヒンドゥー教のシヴァ神の化身であるマハーカーラは、インド密教に取り入れられた。“マハー”とは大(もしくは偉大なる)、“カーラ”とは時あるいは黒(暗黒)を意味するので大黒天と名づく。その名の通り、青黒い身体に憤怒相をした護法善神である。
シヴァ神のマハーカーラがそのまま密教に取り入れたため、初期の大黒天はシヴァと同様に四本の手に三叉戟、棒、輪、索をそれぞれ持った像として描かれた。さらには、ブラフマーとヴィシュヌをも吸収していき、ヒンドゥー教の三神一体(プラフマー・ヴィシュヌ・シヴァ)に対応した三面六臂の憤怒相の大黒天(マハーカーラ)も登場した。
後期密教を継承したチベット仏教では、大黒天(マハーカーラ)の像容は多彩であり、一面二臂・一面四臂・一面六臂・三面二臂・三面四臂・三面六臂などがある。(シヴァに由来しながらも)シヴァとその妻パールヴァティー、もしくはガネーシャを踏みつけてヒンドゥー教を降伏させて仏教を勝利させる護法尊としての姿が主流となった。チベット・モンゴル・ネパールでは貿易商から財の神としての信仰を集め、チベットでは福の神としての民間信仰も生まれた。
日本には密教の伝来とともに伝わり、天部と言われる仏教の守護神達の一人で、軍神・戦闘神、富貴爵禄の神とされたが、特に中国においてマハーカーラの3つの性格のうち、財福を強調して祀られたものが、日本に伝えられた。密教を通じて伝来したことから初期には主に真言宗や天台宗で信仰された。インドでも厨房・食堂の神ともされていたが、日本においては最澄が毘沙門天・弁才天と合体した三面大黒を比叡山延暦寺の台所の守護神として祀ったのが始まりという。後に大国主神と習合した。室町時代になると日蓮宗においても盛んに信仰された。
日本においては、大黒の「だいこく」が大国に通じるため、古くから神道の神である大国主と混同され、習合して、当初は破壊と豊穣の神として信仰される。後に豊穣の面が残り、七福神の一柱の大黒様として知られる食物・財福を司る神となった。室町時代以降は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」の民族的信仰と習合されて、微笑の相が加えられ、さらに江戸時代になると米俵に乗るといった現在よく知られる像容となった。現在においては一般には米俵に乗り福袋と打出の小槌を持った微笑の長者形で表される。
袋を背負っているのは、大国主が日本神話で最初に登場する因幡の白兎の説話において、八十神たちの荷物を入れた袋を持っていたためである。また、大国主がスサノオの計略によって焼き殺されそうになった時に鼠が助けたという説話(大国主の神話#根の国訪問を参照)から、鼠が大黒天の使いであるとされる。
春日大社には平安時代に出雲大社から勧請した、夫が大国主大神で妻が須勢理毘売命(すせりひめのみこと)である夫婦大黒天像を祀った日本唯一の夫婦大國社があり、かつて伊豆山神社(伊豆山権現)の神宮寺であった走湯山般若院にも、像容が異なる鎌倉期に制作された夫婦大黒天像が祀られていた(現在では熱海の古屋旅館に存在する)。
(wikipediaより)
「富貴爵禄 七宝運び 財福豊穣 充ち満ちと」
【参考資料】
『七福神の謎』武光 誠 著
【商品説明】
直筆サインが入った1点ものの掛け軸です。
表装(絵柄)以外の部分も特殊加工の印刷により仕上げてあります。
すべて布製ですので耐久性に優れており、収納もしやすくなっています。
説明の短冊がつきます。(画像はサンプルです)
表装部の大きさ 幅30cm x 高さ60cm
【説明】
インドの神で、仏教に取り入れられ台所の神とされた。大国主命の別の姿ともされる。
ヒンドゥー教のシヴァ神の化身であるマハーカーラは、インド密教に取り入れられた。“マハー”とは大(もしくは偉大なる)、“カーラ”とは時あるいは黒(暗黒)を意味するので大黒天と名づく。その名の通り、青黒い身体に憤怒相をした護法善神である。
シヴァ神のマハーカーラがそのまま密教に取り入れたため、初期の大黒天はシヴァと同様に四本の手に三叉戟、棒、輪、索をそれぞれ持った像として描かれた。さらには、ブラフマーとヴィシュヌをも吸収していき、ヒンドゥー教の三神一体(プラフマー・ヴィシュヌ・シヴァ)に対応した三面六臂の憤怒相の大黒天(マハーカーラ)も登場した。
後期密教を継承したチベット仏教では、大黒天(マハーカーラ)の像容は多彩であり、一面二臂・一面四臂・一面六臂・三面二臂・三面四臂・三面六臂などがある。(シヴァに由来しながらも)シヴァとその妻パールヴァティー、もしくはガネーシャを踏みつけてヒンドゥー教を降伏させて仏教を勝利させる護法尊としての姿が主流となった。チベット・モンゴル・ネパールでは貿易商から財の神としての信仰を集め、チベットでは福の神としての民間信仰も生まれた。
日本には密教の伝来とともに伝わり、天部と言われる仏教の守護神達の一人で、軍神・戦闘神、富貴爵禄の神とされたが、特に中国においてマハーカーラの3つの性格のうち、財福を強調して祀られたものが、日本に伝えられた。密教を通じて伝来したことから初期には主に真言宗や天台宗で信仰された。インドでも厨房・食堂の神ともされていたが、日本においては最澄が毘沙門天・弁才天と合体した三面大黒を比叡山延暦寺の台所の守護神として祀ったのが始まりという。後に大国主神と習合した。室町時代になると日蓮宗においても盛んに信仰された。
日本においては、大黒の「だいこく」が大国に通じるため、古くから神道の神である大国主と混同され、習合して、当初は破壊と豊穣の神として信仰される。後に豊穣の面が残り、七福神の一柱の大黒様として知られる食物・財福を司る神となった。室町時代以降は「大国主命(おおくにぬしのみこと)」の民族的信仰と習合されて、微笑の相が加えられ、さらに江戸時代になると米俵に乗るといった現在よく知られる像容となった。現在においては一般には米俵に乗り福袋と打出の小槌を持った微笑の長者形で表される。
袋を背負っているのは、大国主が日本神話で最初に登場する因幡の白兎の説話において、八十神たちの荷物を入れた袋を持っていたためである。また、大国主がスサノオの計略によって焼き殺されそうになった時に鼠が助けたという説話(大国主の神話#根の国訪問を参照)から、鼠が大黒天の使いであるとされる。
春日大社には平安時代に出雲大社から勧請した、夫が大国主大神で妻が須勢理毘売命(すせりひめのみこと)である夫婦大黒天像を祀った日本唯一の夫婦大國社があり、かつて伊豆山神社(伊豆山権現)の神宮寺であった走湯山般若院にも、像容が異なる鎌倉期に制作された夫婦大黒天像が祀られていた(現在では熱海の古屋旅館に存在する)。
(wikipediaより)
「富貴爵禄 七宝運び 財福豊穣 充ち満ちと」
【参考資料】
『七福神の謎』武光 誠 著
【商品説明】
直筆サインが入った1点ものの掛け軸です。
表装(絵柄)以外の部分も特殊加工の印刷により仕上げてあります。
すべて布製ですので耐久性に優れており、収納もしやすくなっています。
説明の短冊がつきます。(画像はサンプルです)
表装部の大きさ 幅30cm x 高さ60cm
#神 #七個幸運神 #日本 #武 #印度 #掛軸 #藝術 #插圖 #新年 #大黒 #
商品説明
商品情報
送料とその他の情報
- 送料
- 支払方法
-
-
クレジットカード決済





-
コンビニ決済




-
d払い

-
銀行ATM振込(Pay-easy決済)

-
Alipay

-
GMO後払い決済
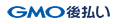
-
クレジットカード決済
- 返品・交換のお知らせ
- 返品・交換のお知らせを見る
- 通報
- この商品を通報